崎山貝塚について
崎山貝塚について
崎山貝塚は縄文時代のムラや貝塚、そしてまわりの環境までもがそっくりそのまま残されていて、当時の生活や文化をさぐることのできる遺跡です。
崎山貝塚の縄文人たちは、大規模な土木工事を行い広場を中心とした計画的なムラをつくっています。さらに、貝塚からは縄文人たちが食べた貝や動物などの骨のほかに、縄文時代でも古い時期の“骨や角で作った道具”(骨角器)も数多く発見されています。
このようなことから、崎山貝塚は全国的にも貴重な遺跡であると認められ、平成8年7月16日に国の史跡として指定されました。今後は崎山貝塚を将来にわたり保存するとともに、史跡公園として活用することとなりました。
崎山貝塚の発掘調査
崎山貝塚ではじめての発掘調査が行われたのは大正13年(1924)のことでした。当時、国の柴田常恵調査員、岩手県の小田島禄郎調査員及び地元研究者らは崎山貝塚を発掘調査し、貝やクジラの骨などを発見しています。これら先生方による発掘調査によってこの遺跡は貝塚であることがはっきりしました。
この後、宮古市では崎山貝塚を保存するために、昭和61年度から発掘調査を継続的に実施しています。
崎山貝塚の立地と周辺遺跡
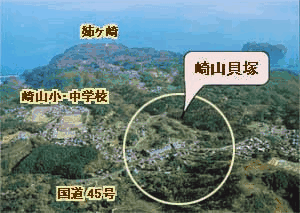
崎山貝塚は姉ケ崎というみさきに向かってのびた台地のうえにあり、海からの高さは120メートルで、海辺からは約1.5キロメートルはなれています。
縄文人たちは海でとった魚や貝をわざわざこの台地のムラまで運びあげてくらしていました。
崎山貝塚のまわりにはたくさんの遺跡がありますが、崎山貝塚はムラや貝塚の大きさなどからこの遺跡群の中心的な遺跡であると考えられています。
この記事に関するお問い合わせ先
教育委員会 文化課
〒027-0097
岩手県宮古市崎山1-16-1
電話番号:0193‐65-7526








更新日:2024年12月23日