啄木と賢治、岩手が生んだ二人の天才は宮古で何を思ったか
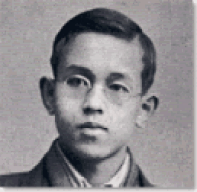
石川啄木
人生の深い哀感を歌った天才歌人・石川啄木(1886年〜1912年)。小学校の代用教員や新聞記者などをしながら郷里や北海道の各地を転々としていましたが、1908年春、文学生命を賭けるべく船で単身上京をはかります。その途上で寄港したのが宮古港。同年4月6日の啄木の日記には、その祈りのことが鮮明な筆致で記されています。
《…十時頃瓦斯が晴れた。午后二時十分宮古港に入る。すぐ上陸して入浴、梅の蕾を見て驚く。蕾許りではない、四方の山に松や杉、これは北海道で見られぬ景色だ。…》

賢治・啄木の記念碑
啄木がつづったこの宮古上陸の日記は、記念碑に刻まれています。
この時上京して、二度と生きて故郷の土を踏むことのなかった啄木。
日記からは、昔日の宮古の空気とともに、悲壮な決意を胸に秘めた歌人の心が、まざまざと浮かび上がってくるようです。
(注意)啄木の記念碑は鍬ヶ崎地区の七滝公園(宮古漁協ビル敷地より移設)に、
賢治の記念碑は浄土ヶ浜に建てられています。
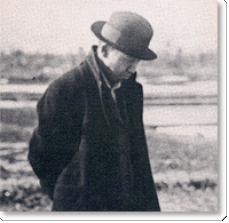
宮沢賢治
啄木の寄港から九年後の夏、当時まだ盛岡高等農林の学生だった宮沢賢治(1896年〜1933年)が宮古の地を踏みました。花巻町有志とともに、工場見学と地質調査を目的とした来訪でした。この時に賢治が詠んだ歌が次の一首。
うるはしの
海のビロード 昆布らは
寂光のはまに 敷かれひかりぬ
賢治が見た宮古の浜辺の風景は、今もこの町に残っています。
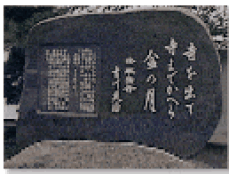
吉川英治句碑
(旧愛宕小学校敷地内)
吉川英治句碑
「どうなるものか、この天地の動きが。もう人間の個々の振る舞いなどは、秋風の中の一片の木の葉でしかない。なるようになってしまえ。武蔵は、そう思った。」
この書き出しで始まる「宮本武蔵」の作者吉川英治は、昭和10年に本照寺に滞在しています。
碑に刻まれている「寺を出て 寺までかへる盆の月」の句は、その時の詠まれたものです。
(注意)本文中の文字は、「啄」の文字で代用しています。
お問い合わせ
産業振興部観光課
電話: 0193-62-2111ファクス: 0193-63-9120
この記事に関するお問い合わせ先
商工労働観光部 観光課
〒027-8501
岩手県宮古市宮町一丁目1-30
電話番号:0193‐62‐2111








更新日:2024年12月23日